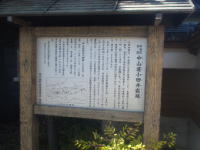ギャラリー村積庵
中山道(2回目)〔前半〕
写真集中山道(2回目)〔前半〕 もご覧ください。
***サムネイル画像をクリックすると、大きな画像を見ることが出来ます***
***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***
***元に戻る場合は、ブラウザーの”戻るボタン”で戻ってください***
| 浦和 〜 桶川 (2日目:約8時間、推定距離 約20km) | ||||||
2013年9月24日 |
||||||
気象庁も認めた異常気象の夏が終わり、この後も秋雨が少なくて、幸い中山道(2回目)〔前半〕は、天候に恵まれて歩くことが出来ました。 浦和から与野・さいたま新都心・大宮と、建物や道路整備が進み、昔の街道の面影は無いようですが、街中には青面金剛や地蔵尊などが残されていました。 〔写真:近代的なビルディングが建ち並ぶさいたま新都心〕
また、珍しい例としては、大宮市内の歩道に設置された、塩地蔵と子育地蔵の案内石碑が立派で驚きました。 60才になってからのパート仕事で、石仏の調査作業をお手伝いしたこともあり、キチンと拝んで来ました。 〔写真:歩道に設置された塩地蔵と子育地蔵の案内石碑〕
武蔵一ノ宮として、氷川神社の境内や参道は広大で、三の鳥居からでも約1.5km歩き、約1時間後に中山道へ戻る寄り道になりました。 「鉄道博物館」を左手に見て、先へ進みましたが、加茂神社、南方神社、愛宕神社と、この後も多くの神社や街中の石仏が見られました。 中山道を軸にして生活していた、この辺りの地方の方々の信仰心の高さと裕福さが伺えます。 〔写真:朱塗りで参詣者を迎える氷川神社の楼門〕
上尾駅前には、商業施設や噴水があり、ゆっくり休憩させてもらいましたが、大きなタワーマンションが目に入りました。 ちょうど売り出し中のようで、案内板や旗が目立ちましたが、この後通過した各駅前付近にも、新築された大きなマンションが建っていました。 昔の宿場町が、鉄道の利便性により、大きく姿を変えつつあるのだと、世の中の移り変わりを感じてしまいます。 〔写真:売り出し中の上尾駅前のタワーマンション〕
この辺りの上尾宿の昔を偲ぶ建物などが無くなっており、道路整備と合わせて記念碑のように残されたのでしょう。 前回から比べると、各地で道路整備が進められており、新しい中山道となる国道17号が大きな幹線道路として整備されています。 さらに、中山道として残されていた旧道も、最近になって沿道の古い家を取り壊して、都市計画の一部として、拡幅など道路整備がされている状況が多く見受けられました。 〔写真:道路整備に伴い設置された上尾宿上町の平成の道標〕
その道標にも記載されていた、昔の旅籠がそのままの状態で残る「武村旅館」が見えてきました。 桶川宿には、古い建物が多く残されていますので、旧街道歩きが好きな人には、見逃せない町だと思います。 この日は、桶川駅から帰宅しますが、順調に歩いてきましたので、お土産に地元の銘菓「おき川」と「五家宝」を購入し、予定よりも1時間早く帰ることが出来ました。(25,000歩) 〔写真:昔の旅籠がそのままの状態で残る「武村旅館」〕 |
||||||
| |
| 桶川 〜 熊谷 (3日目:約9時間、推定距離 約23km) | ||||||||
2013年10月8日 |
||||||||
将来計画として、高崎線の東京駅乗り入れがあるようですが、「是非実現して欲しい」と、田舎旅行者から要望の一言! 気温は、約29℃と高めですが、晴れ時々曇りと天候に恵まれて、少々時間は遅れても桶川駅から気持ち良く歩き始めました。 桶川の街並で、早速目に入ったのが、古い店構えのお茶屋さんでしたし、倉庫と一体化した古い店なども、見るだけで嬉しくなります。 〔写真:珍しい倉庫と一体化した古い店〕
前回もお世話になった宿場案内地図のある「桶川宿 手洗い処」や、近くにある「中山道宿場館」前の様々な掲示物からも、親切さが伝わってきます。 そうは言っても、桶川駅付近にも、大きなマンションが建ちはじめていて、他の町と似たり寄ったりで、新旧が混在しているように感じました。 今後の街づくりの過程で、上手に古いものを残していただき、住む人にも快適で、訪問者にも親切な街づくりをお願いしたいと思います。 〔写真:前回もお世話になった宿場案内地図〕
鴻巣宿の産業観光館「ひなの里」には、広い中庭や休憩所もあり、車で訪れても楽しめそうです。 この後にもいくつか見られましたが、古墳を浅間神社として祭ってあるなど、この地方の古い時代の開拓と信仰の成り立ちが偲ばれます。 昼食は、近くの和食レストランで、旬の「さんまの唐揚げおろしランチ」を食べて、元気をつけました。 〔写真:休憩所やお土産処の産業観光館「ひなの里」〕
また、最近建てられた道標には、朱色の彫りこみで中山道と鴻巣宿が目立つようにしてありました。 「彩の国 平成の道標」の一つのようですが、江戸や京都までの距離も入っており、このような道標は歩くための目標になり大歓迎です。 中山道全体に統一した道標があれば、旅行者としては助かりますが、地方自治優先の現代には合わない希望かもしれません。 〔写真:宿場外れの分かれ道に最近建てられた道標〕
写真の堰と裏手には顕彰碑のある小さな公園ですが、ベンチやトイレもあり、改めて感謝して休ませてもらいました。 この後、地蔵堂の横から荒川の土手に上がりますが、ちょうど夕刻になり、ジョギングの人や犬を連れた散歩の人の姿が、かなり見られました。 近くには、いくつか大きなマンションがありましたので、住人の方々の憩いの場でもあるようです。 〔写真:往復共にお世話になった榎戸堰公園〕
遠くまで見渡せますので、土手道を散歩する人々や、バイク・自転車が遠くに小さく見えて、気持ち良く歩くことが出来ました。 前回は、雨の中で風もあり、土手道の上を歩けずに、一段下の車両用の道路を歩いたことを思い出して、改めて天候に感謝です。 夕刻も近く、薄曇りでしたが、かえって歩き易い条件で、思わず足取りもゆっくりになってしまいます。 〔写真:「久下の長土手」と呼ばれた広大な荒川の土手道〕
この広大な堤防が決壊するとは信じられない思いですが、昭和22年当時に、この付近で決壊して、関東平野の広い面積が水に漬かったとのことです。 改めて治水事業の大切さを思い知らされますが、一方で議論を呼んだ「スーパー堤防」の看板には、黒い塗料でいたずらがしてありました。 地震や台風などの自然災害に備える防災施設の”目標設定”は、本当に難しい判断を伴うものだと感じてしまいます。 〔写真:近くにはマンションや多くの家が見られる「決潰の跡」の石碑〕
陸上交通の発達した現代では考え難いのですが、昔の舟運は物資運搬の柱でしたから、この辺りも江戸の堀まで繋がっていたのでしょう。 暗闇の中を懐中電灯を頼りに進んでいると、対向して来た車の女性運転者から北本への道を尋ねられましたが、とても歩いてきた道を行くのは無理なため、熊谷に戻り国道17号を使うことをお勧めしました。 〔写真:荒川の舟運で栄えた百年前の久下新川村の様子を表した案内板〕 再び歩き始めて、JR新幹線・在来線や秩父鉄道の線路を渡り、熊谷駅近くのホテルに予定通りチェックイン出来ましたので、夕食は近くでラーメンを食べ、明日に備えてぐっすり眠りました。(30,000歩) |
||||||||
| |
| 熊谷 〜 本庄 (4日目:約8時間、推定距離 約20km) | ||||||||
2013年10月9日 |
||||||||
中山道の石碑が建つ百貨店前で、信号交差点の横断歩道を渡り、向かい側の細い道に入りますが、少し先で再び国道17号に合流します。 熊谷警察署を過ぎてから熊谷市内を抜ける辺りで、国道17号を左に外れてすぐに、大きなけやきが残る「新島一里塚」や「忍領石標」のある旧道に入ります。 この後も、次の深谷宿までは、国道17号と途中で交差する旧道を進んで行きます。 〔写真:中山道が店頭を通る八木橋百貨店〕
改めて今回の地図を見直すと、教えてもらった道の方が、この先で国道17号を斜めに横切り、素直に中山道の旧道に繋がります。 当時、国道17号が工事中だったのか? 前回はなぜか勘違いして、国道17号の南側を大きく迂回して歩いていたようです。 同好の方々から間接的に教えて頂いたようで、教えて頂いた方にお礼を言って、正しい道に変更して、先に進みました。 〔写真:大きなけやきが残る「新島一里塚」〕
すぐ手前で石碑に気が付き写真を撮っていましたが、小さな松でしたから感激も無く、なぜ有名なのかと不思議に思いました。 帰宅してから調べてみると、古い写真には大きな一本松が映っていましたので、遊女を偲ばせる老松が伐採されて、代替わりしているようです。 深谷宿に入ると大きな常夜燈が迎えてくれ、さらに中心部へ進むと、前回には無かったのですが、市街地活性化のため、七ツ梅酒造跡地に新設された「酒蔵の映画館 深谷シネマ」が目に入りました。 〔写真:新設された「酒蔵の映画館 深谷シネマ」〕
新旧のお店の建物が隣り合い、新しいお店が道路から後退して建てられていますが、近くに掲示されていた区画整理事業構想図によると、幅広の歩道が出来るようです。 深谷宿中心部の近代化構想ですから、完成が楽しみですが、歩く旅行者としては、建物や植栽による日陰作りの配慮も希望します。 中心部は区画整理事業の工事中でしたが、西側には昔の深谷宿が残されていました。 〔写真:定休日で残念だった「翁最中」で有名な糸屋菓子店〕
深谷宿の東西にある常夜燈は、天保11年(1840年)建立の中山道最大級とのことで、スラリとした姿の良い石造物と感心しました。 また、枡形も道路に邪魔にならないように残され、小さなお堂や石像も、お寺と一緒に上手に残されていました。 中心部の区画整理事業が、この辺りまで及ぶ時には、地域の方々のご理解を得て、文化財として新しい街並に融けこむよう工夫して頂きたいと思います 〔写真:深谷宿の東西に残る大きな常夜燈〕
この地区には、多くの寺院や神社があり、田園風景も広がっています。 こうした土地柄もあるのでしょうか、平成23年建立の石碑に、中山道の古道を紹介してありました。 また、古道沿いにある「百庚申」の案内板も、判り易く整備されていて、地元の方々の熱意が伝わってきます。 〔写真:中山道の古道を紹介した石碑と百庚申案内板〕
有り難く思いましたので、ご案内通りに古道を進み、「百庚申」の石造物を拝観出来て、幸せな気持ちになりました。 この後通った「滝岡橋」も、近代の石造文化財と言えるもので、少し古風ですが田園風景の中に残る姿は、大切に残したいものです。 この橋を渡り、本庄市に入ってすぐの牧西地区の中山道沿いには、石仏と石碑が並んでいます 〔写真:古道を進むと拝観出来る「百庚申」〕
地域の方々の熱意が無いことには、こうした路傍の文化財が失われてゆきますので、今後ともよろしくお願いしたいものです。 この辺りで2日間通して約30km歩いたことになりますが、日頃の運動不足や年齢のためか、最近はこれ位の距離になると休憩して、棒の様になった足(腿とふくらはぎ)のマッサージが欠かせません。 〔写真:本庄市牧西の中山道沿いに並ぶ石仏と石碑〕 一休みして本庄駅に向い、その途中で火事現場に差し掛かってしまいましたが、消火活動のため警察による規制線が張られていたものの、ほぼ鎮火して歩行者はOKとのことで事なきを得ました。 こんな経験は初めてで印象的でしたが、無事にJR本庄駅から帰路に付くことが出来ました。(26,000歩) |
||||||||
| |
| 本庄 〜 高崎 (5日目:約7時間、推定距離 約19km) | ||||||||
2013年10月30日 |
||||||||
うっかり温度・高度を測定出来る腕時計を家に置き忘れてきてしまい、翌日の松井田までの行程にも使えず、準備の悪さに反省しきりです。 本庄市内を歩き始めて、晴れた空と爽やかな風が吹く天候のお陰で、忘れた腕時計の出番も無さそうで、多少救われた気持ちになりました。 旧中山道である中央通りには、銀行の支店が多く、本庄市が埼玉北部の中心的な町なのだと再認識しました。 また、旧本庄商業銀行の煉瓦倉庫を改装した菓子店と、「ほんじょうかるた」の石碑を見て、地域の伝統を愛する土地柄に感心しました。 〔写真:旧本庄商業銀行の煉瓦倉庫を改装した菓子店と、「ほんじょうかるた」の石碑〕
左の写真では、中央の小山(古墳)に樹木が繁り、参道・赤い鳥居と共に、古墳を発掘した内容を示す案内板が掲示してありました。 先ほどからも、埼玉北部の地域について、伝統的なことを尊重する土地柄と述べましたが、この事例でも明らかでしょう。 各地で開発が進んでいて、この地域も巻き込まれると思いますが、うまく文化財を残す形で進まれるよう、伝統を重んじる土地柄に期待します。 〔写真:浅間神社として祭っている古墳(発掘済み)〕
上武二州の境にある橋が見えてくると、「見透灯籠」が目に付きますし、いわれを記載したプレートも、旅人の目を引きます。 橋の両側に設置してある灯籠ですが、埼玉側の灯籠には草の”つる”がからまり、空の青色とも釣り合っていました。 群馬側の灯籠も立派な姿でしたから、こちらも気に入りましたので、写真を何枚も撮りました。 〔写真:草のつるがからまった埼玉側の灯籠〕
前回は雨の中でしたので、暗い気持ちになり往時の悲惨ないくさを偲びましたが、今回は天候が良くて、そうした雰囲気は感じませんでした。 しかし、前回には気が付かなかった句碑や小さな石碑を見ると、改めて悲惨ないくさと、弔った人々の気持ちが伝わってきます。 この後訪れた新町宿は、前回は通り過ぎただけだったのですが、今回は天候が良く、休憩も出来ましたので、大きく印象が変わりました。 〔写真:「神流川古戦場跡」の石碑がある小公園〕
以前にも、娘から里帰りのお土産にもらいましたが、東京土産とばかり思っていたのが、高崎産とは初めて気が付きました。 新町宿は、この工場前から右側の旧道を進みますが、芭蕉の句碑や八坂神社と諏訪神社に、いくつかのお寺もあり、往時の宿場町としての隆盛さを偲ばせます。 〔写真:チョコラスクで有名な「ガトーフェスタハラダ」の工場〕
明治天皇の行在所や記念碑は、中山道のあちこちに残されていて、各地のお迎えも大変だったでしょうが、明治天皇の行動力もさすがです。 明治維新後の国内統治のために、各地に旅行して盛大なお迎えを受けたことが、皇室への親密さや尊敬につながり、明治時代の日本が発展した一助になったのでしょう。 それ以降は、尊敬から謹厳な扱いに重きが置かれていましたが、新憲法以降は”象徴”として、再び親密さを重視されているようです。 〔写真:円錐形の屋根を持つ休憩所と、明治天皇行在所が一緒になった公園〕
この先の烏川沿いは、ところどころ旧道も残っているようですが、前回もはっきり判りませんでしたので、今回は見晴らしの良いサイクリングロードを歩きました。 午後3時過ぎに雨雲も出て、空が暗くなってきましたので、柳瀬橋を渡ってから、右手にある渡し場跡までは省略して、先を急ぐことにしました。 午後4時過ぎに倉賀野宿に入りましたが、日光例幣使街道との追分では、前回と同様に雨に降られて、閻魔堂で雨宿りとなりました。 〔写真:日光例幣使街道との追分と、後ろは雨宿りした閻魔堂〕
この後は写真撮影をあきらめて、夕闇の中を高崎駅に向けて市内の道を急ぎました。 ほとんど大きな通りでしたから、街路灯にも助けられ、懐中電灯も持っていましたので、歩道を安全に歩くことが出来ました。 ”ひらがな”の「あら町」交差点から、高崎駅前の通りに入り、駅前のホテルに午後6時に無事到着し、駅構内の飲食店で夕食を済ませて寝みました。(25,000歩) 〔写真:今回は前泊も含めてお世話になった高崎駅西口(翌日に撮影)〕 |
||||||||
| |
| 高崎 〜 松井田 (6日目:約8時間、推定距離 約21km) | |||||||||
2013年10月31日 |
|||||||||
北上する道沿いの市営中央駐車場の板塀に、新町宿から坂本宿まで7枚の、中山道各宿の浮世絵の模写が並んでいて嬉しくなりました。 本町三丁目を左折すると、土蔵の旧家があり、その先の細い道には、地名「高崎」のいわれに関係する恵徳寺や、旧家の岡醤油店があり、常磐町角の山田文庫なども、いずれもゆっくり拝見したいところですが、写真を撮るだけにして先を急ぎました。 昔の名残なのか(?) 松林を過ぎると、国道が立体交差している「君が代橋」を渡り、すぐ右の旧道に入ります。 〔写真:国道が立体交差している「君が代橋」〕
若宮八幡宮を過ぎると、板塀付の蔵と立派な門構えの「上豊岡の茶屋本陣」が見えてきます。 この先で碓氷川沿いの国道18号に出ますが、八幡宮の大鳥居が見える辺りでは、碓氷川の土手道を歩き、再び国道18号に戻った後、板鼻宿への道に入ります。 板鼻宿からは安中市に入り、木杭風の道標が道案内をしてくれますし、公民館付近には本陣跡の石碑や、石造物が残る広場もありました。 〔写真:板塀付の蔵と立派な門構えの「上豊岡の茶屋本陣」〕
道の反対側に廃業したお店がありましたので、渡し場を再現・記念した商売をされていたのか? 今は、鷹之巣橋が架かっていますが、往時は川止めが多くて、板鼻宿が繁盛していたようです。 橋を渡り、右に入った細い道には、中宿があり、渡し場への道と、古い道標や石像がいくつも残されていて、往時を偲ばせます。 〔写真:往時を説明する古ぼけた掲示板とボートが置いてある碓氷川の渡し場〕
国道18号越しに見える、丘の上に広がる「東邦亜鉛安中精錬所」も、現在は公害防止協定を結び、地域と協調されています。 この日の帰路に、安中駅から新人らしいスーツ姿の若い人達が多数乗車するのを見かけて、地域経済を支える企業との印象を持ちました。 中宿の西にある久芳橋を渡り、国道18号から左に分かれる旧道を進むと、安中の市街地に入ります。 〔写真:国道18号越しに丘の上に広がる「東邦亜鉛安中精錬所」〕
したがって、旧安中藩関係の建物は、中山道の右側に位置していることが多く、写真の茅葺屋根の「旧安中藩武家長屋」も、150m程右手の方にありました。 近くに茅葺の「郡奉行役宅」もあり、観光客も多数見かけましたし、案内板によるとNHK大河ドラマ「八重の桜」も、安中に縁があるようです。 また、安中宿の西側には、「新島襄旧宅」や「便覧舎址碑」などが、案内板や旗などで示されていました。 〔写真:茅葺屋根の「旧安中藩武家長屋」〕
その大きさが記憶に残っている杉並木は、その先で国道18号と交差する旧道を進むと、ようやく行く手に見えてきました。 案内板によると、「中山道しのぶ 安中杉並木」と安中かるたに謳われる天然記念物「安中原市の杉並木」は、残念ながら14本が残るのみだそうです。 〔写真:安中かるたに謳われる天然記念物「安中原市の杉並木」案内板〕
前回の中山道歩きでも、気に入った光景の一つなのですが、前回の時よりも本数が減ったように感じました。 雷や病害虫などにより、減少はやむを得ないと思いますが、何とか保存をお願いしたいものです。 この先も旧道が続き、「明治天皇小休所」や「八本木立場」の旧家が残り、松井田宿まで木杭風の道標と道祖神が道案内をしてくれました。 〔写真:中山道をはさみ、残りの大杉が天に向けて直立〕
松井田宿の下町に差し掛かると、旧家の前に丸い形の軽自動車が、車のCMでも見ているように停められていました。 長く自動車産業に勤めていましたので、ついつい車を見かけると目を留めてしまうのですが、この写真は昔のCMを思い出させます。 〔写真:CMでも見ているように、旧家前に停められていた丸い形の軽自動車〕
この日は、松井田宿の西側にあるJR西松井田駅まで歩き、信越本線で高崎まで戻り、帰宅時間を早めるために、上越新幹線を利用したので、東京まで約1時間で到着です。 日本橋から歩き始めて6日間分のほとんどの区間を、新幹線ではわずかに1時間ですから、改めて新幹線の速さに敬服して、東京駅で「タンタン麺」を食べてから岡崎へ帰宅しました。(30,000歩) 〔写真:「松井田町商工会館」など古い建物が残り、JRの駅も2つある松井田宿の案内板〕 |
|||||||||
| |
| 松井田 〜 軽井沢 (7日目:約9時間、推定距離 約21km) | ||||||||
2013年11月5日 |
||||||||
秋らしい晴天の下、早速駅前から歩き始めて、すぐに「補陀寺」の前で足が止まりました。 門が見事だったのと、北条氏に仕えた大道寺政繁の菩提寺との案内があったからです。 碓氷峠の山中では、豊臣秀吉による北条攻めの北国勢が進軍し、大道寺軍と戦った歴史が残されています。 〔写真:北条氏に仕えた大道寺政繁の菩提寺である「補陀寺」〕
この後、前回は見過ごした「五料の茶屋本陣」が目に入り、信越本線の踏切を越えて「お東」「お西」の両本陣前まで往復しました。 その後も、中山道は信越本線と交差しながら進んで行きますが、臼井小学校付近で地元の方と話す機会がありました。 通り掛りの挨拶をしたのですが、見事な景色の妙義山について、この辺りでは「裏妙義」と呼びますと教えて頂きました。 〔写真:この辺りでは「裏妙義」と呼びますと教えて頂いた見事な景色の妙義山〕
横川といえば、現在「鉄道文化むら」がある信越本線の終点ですが、もっと有名なのは「峠の釜めし」の”おぎのや本店”でしょう。 前回は帰り道でしたから、「峠の釜めし」を手にぶら下げて歩きましたが、今回は碓氷峠を越えますので、メニュートップの「カツ丼」を頂きました。 ほとんどの人が釜めしを食べますので、返って迷惑だったでしょうが、笑顔で対応してくれた上に、峠越えを励まして頂きました。 〔写真:「峠の釜めし」で有名な”おぎのや本店”〕
現在は、安中藩が管理した東門が復元されているようで、「安政遠足」の際に関所祭りが開催されるとのことです。 この先も細い上り道が続き、坂本宿までには、薬師坂など少しずつ上り道が、キツクなってきます。 広い真っすぐな道路(国道18号)に出ると、その先も上り道で、上信越自動車道をくぐると、長い坂道に作られた坂本宿に入ります。 〔写真:東門が復元されている「碓氷関所跡」〕
いくつか本陣がある大きな宿場だったようで、「佐藤本陣跡」もその一つですが、立派な建物で現在も住まわれているように見えます。 他にも旅籠や屋号のある建物や、地元の俳人などを紹介する案内板がいくつもあり、文化財を大切にされている町という印象です。 町外れまで来ると、一旦国道18号ともお別れで、浄水場の横の地道を歩いて、「旧道日和」の看板がある休憩所で再会です。 〔写真:立派な建物が残る「佐藤本陣跡」〕
この「旧道日和」の看板は新しい縦長のもので、以前は横長の大きな看板が、この休憩所付近にあったはずと、うろ覚えの記憶です。 帰宅して確かめてみると「旧道日和」の大きな看板については、前回の写真に残るのは、峠の熊野神社付近だけなのです。 こちらの休憩所付近にあったものは、同じなので撮影を省略した記憶もあるので、松井田町から安中市に変わる際に、変更されたようです。 〔写真:向って左の道から山道が始まる「旧道日和」の看板がある休憩所〕
前回は6月で深緑の中、突然坂本の町が見える快感を味わいましたが、今回は11月で落葉と紅葉が、”明るい覗き”を見せてくれました。 碓氷峠は、軽井沢側が短く急で、坂本側からは長い上り道が続きますが、上り始め以外は緩い上りで、比較的楽に歩くことが出来ました。 途中で、対面からマウウンテンバイクで降りてくる男女や、老夫婦が歩いてきましたので、軽井沢側から来る人も多いのではと感じました。 〔写真:11月で落葉と紅葉が、”明るい覗き”を見せてくれた「坂本の覗き」〕
終点は、熊野神社がある”峠”で変わりませんし、この程度の変更があっても、とても大変なマラソンで、本家にも負けないものだと思います。 神社前で軽井沢から犬連れで散歩されていた方から、「旧道が難しいらしいので、日暮れ前に下りた方が良いですよ」とアドバイスを頂きました。 案の定で、旧道を示す案内板を探しながら沢に下りて、途中で案内板が見当たらず、夕闇も迫りましたので、あきらめて舗装路に出ました。 最後は、18時頃に暗闇の中、宿泊先の軽井沢駅前のホテルに入り、「鶏カツ定食」を食べて寝みました。(31,000歩) 〔写真:有名な「安政遠足」の終点でもある”峠”の熊野神社〕 |
||||||||
| |
| 軽井沢 〜 佐久平 (8日目:約8時間、推定距離 約19km) | ||||||||
2013年11月6日 |
||||||||
駅前のホテルを出て、六本辻交差点(ロータリ)を過ぎてから右手に広がるホテル「ロンギングハウス」は、大きな別荘の雰囲気を出していました。 軽井沢は、観光などで通り過ぎることが多く、とても住む立ち場になれない町だと思いますが、やはり高級感が漂います。 「市村記念館」のある「雨宮御殿」の門前を過ぎると、細い旧道に入り中軽井沢に向かいます。 〔写真:大きな別荘の雰囲気を出しているホテル「ロンギングハウス」〕
今回の中山道は、天候に恵まれているのですが、この浅間山の姿も含めて、かなり信州の山々を写真に撮ることが出来ました。 これまで雨男と思っていましたが、勝手な思い違いのようで、改めて天候の良い時期に、旅行するべきだと考え直しました。 〔写真:青空の下で、くっきりと姿を現した浅間山〕
借宿近くで国道18号に旧道が寸断されますが、その先も借宿の遠近宮を過ぎて、追分近くまでは旧道を進みます。 追分の交差点付近は、国道18号を歩きますが、歩道があり安全ですし、一里塚を過ぎると、追分宿方向に旧道が分かれます。 追分宿の入り口には、整備された追分公園があり、浅間神社の境内にある芭蕉の句碑や「追分節発祥の碑」など、観光客も楽しめます。 〔写真:浅間神社の境内にある「追分節発祥の碑」〕
この「旧街道一人歩き」では、興味が湧くものも時間の関係で、残念ながら素通りとなってしまいます。 記念館入り口付近の写真を撮りながら、この次は車でゆっくり来ようと考えてしまうのは、やはり年齢のせいかとボヤキが出ます。 浅間山登山口もこの先にありましたが、噴火の恐れがあり、入山禁止区域があるようです。 〔写真:宮崎アニメ「風立ちぬ」にも取り上げられた「堀辰雄文学記念館」〕
前回は、この有名な道標があっても読み方が判らず、HP掲載時に勉強しなおしましたが、いまだに歴史通には程遠いレベルです。 北国街道との分かれ道となりますが、昔の人達の分かれ道の作り方は、地形に合わせて斜めに分岐することが多いですね。 旧街道を歩く趣味を持つようになってから、家の近くの道でも、交差具合で旧道なのか考えるようになってきました。 〔写真:追分宿の代名詞のような「分去れ(わかされ)」〕
軽井沢付近から、「中部北陸自然歩道」の道標が道案内をしてくれますので、かなり先の和田峠まで安心して進めます。 この日は、佐久平を終点に進みますが、途中に小田井宿と岩村田宿があります。 特に、小田井宿は本陣跡など街並みの保存が行われていて、昔の宿場を偲ばせます。 〔写真:街並みの保存が行われている小田井宿の本陣跡〕
本陣、脇本陣が各1軒と小規模な宿場だったことが、現在も残されている理由の一つかもしれません。 案内板は通り過ぎた東側にも建っていましたが、その説明の中に、明治以降両側にあった用水路を南側のみに変更したとありました。 文化財としての価値も大切ですが、地域の方々の生活も、より大切ですので、釣り合いを取って保存を継続していただきたいものです。 〔写真:高札場跡に建っていた小田井宿案内板〕
勉強不足は、この有様でも判りますが、目に留まるものを調べて勉強するのも救いになりますので、お許しいただきたい。 次の岩村田宿は、大きな町に変貌していますが、街中にコンシェルジュを置くなど、史跡への理解が深い町だと感じました。 岩村田を抜けた浅間総合病院横に、何代目かの「相生の松」も石碑と共に残されていました。 ここからJR佐久平駅に向い、長野新幹線で長野まで行き、特急「しなの」に乗り換えて岡崎まで、約4時間の帰路に付きました。(22,000歩) 〔写真:浅間総合病院横に残されている「相生の松」〕 |
||||||||
| |
| 佐久平 〜 長久保 (9日目:約9時間、推定距離 約22km) | ||||||||||||||
2013年11月19日 |
||||||||||||||
駅前のホテルに泊まりましたが、夕食のため外出すると、寒空の下、駅前の公園の電飾とイオンモールの照明がキレイでした。 JR佐久平駅の近くには、ホテルや大型のスーパーなどが進出していて、近代的なイメージを創り出していました。 翌朝は、7時30分にホテルを出て、晴れでしたが北風の強い中、浅間病院西の交差点から中山道に入りました。 〔写真:寒空の下、キレイだった駅前の公園の電飾とイオンモールの照明〕
千曲川を前にして、宿場の面影を留める本陣や町屋と、舟をつないで橋にした「舟つなぎ石」が残っています。 明治以降に架けられた中津橋には休憩所があり、周囲の山並みを展望することが出来ます。 また、河岸段丘を上り、塩名田宿を振り返ると、街並みが一望できて、往時の中山道を彷彿させました。 〔写真:舟をつないで橋にした「舟つなぎ石」〕
すぐ近くに一里塚跡もありますので、往時の人々も一服して眺めていたのでしょう。 しばらく歩くと、佐久市役所支所があり、トイレを借用出来ました。 この時期に歩くと、トイレが近くなりますので、コンビニや公共のトイレがあると大助かりです。 〔写真:浅間山の眺望が良く、石仏や句碑が並ぶ広場〕
見事な木造建築の文化財と、狛犬や石碑などが往時の繁栄を示していて、宿場名になった理由が判りました。 八幡宿については、前回は一本並行する裏道を歩いたようで、今回西側の道標を確認し、矢印の向きが斜めのため、勘違いしたことに気が付きました。 今回は真っすぐに歩き、本陣跡や宿場の面影を残す街並みが見られましたので、八幡宿を再認識出来ました。 〔写真:見事な木造建築の文化財と、狛犬や石碑などが往時の繁栄を示す高良社のある八幡神社〕
次の望月宿の道案内に従い、細い旧道を入ると、百沢の旧家が並ぶ中に、宮廷貴族風の「祝言道祖神」と案内板にもある珍しい道祖神を見つけました。 これまでも、双体の道祖神は沢山見かけましたが、古風な服装と古い石材の組み合わせは初めてです。 写真には撮りましたが、もう少し調べてみれば良かったとは、後になってからの後悔でした。 〔写真:宮廷貴族風の「祝言道祖神」と案内板にもある珍しい百沢の道祖神〕
昔の水害で、中山道のルート変更があったようですが、「望月宿のみち案内」の案内板通りに歩きました。 望月宿は、昔の雰囲気を色濃く残す宿場町で、中山道以外にも散策に良い道が多いようです。 長坂橋を渡り、細い道を少しだけ上ると、宿場の通りに出ます。 〔写真:見所と地図を示す「望月宿のみち案内」の案内板〕
カツ丼をオーダーする際に、店主さんから”雁喰(がんくい)味噌”の説明を受けて、好奇心の強い性格ですから、それを注文しました。 お店に掲示してあるパンフレットを見ると、望月宿の食堂仲間で、”駒月カツ丼”として、各店で特徴のあるカツ丼を提供しているようです。 「伊勢屋」の”雁喰味噌”カツ丼は、ソースカツ丼風の見かけで、塩辛い味噌の味のため、油濃さを感じない、サッパリした味でした。 〔写真:お店に掲示してある”駒月カツ丼”と”雁喰味噌”のパンフレット〕
その中から一枚をご紹介すると、「脇本陣 鷹野」の看板が出ている旧家の写真です。 延焼防止のたて壁が現代風ですが、全体的な雰囲気が気に入ったのと、背景に望月宿の道が映っていたので選びました。 また、重要文化財「真山家」も木造建築物として、ほぼ原形を留めている貴重なものだと思いました。 〔写真:「脇本陣 鷹野」の看板が出ている旧家〕
旧道を「茂田井宿入口」の方へ、さらに右に入って行くと「茂田井間の宿 散策マップ」案内板が判りやすく、宿場内を示してくれます。 神明社から先に、まず武重本家酒造の建物が並び、次に大澤酒造と「しなの山林美術館」が続きます。 武重本家酒造の白色の蔵が続く景色は、両側の用水路も残り、時代をさかのぼった気分になれます。 〔写真:判りやすく、宿場内を示してくれる「茂田井間の宿 散策マップ」案内板〕
季節が良ければ、観光客も多そうな、「茂田井間の宿」一番人気の場所でしょう。 杉玉の下がる門構えが、誘惑してきましたが、やはり素通りして先を急ぐことにします。 現在は、亀甲模様のコンクリート敷きとなった石割坂の先に、一里塚があり、茂田井間の宿の出口になります。 〔写真:杉玉の下がる大澤酒造と「しなの山林美術館」入り口〕
芦田宿には、何箇所か「芦田宿散策マップ」が建ち、判りやすく案内していますし、交流館も整備されていますが、残念ながら休館日でした。 代わりに立科町役場まで足を伸ばして、休憩させてもらいました。 芦田宿の本陣は、個人の家の一部として保存され、建物も良い状態が保たれているようです。 〔写真:判りやすく案内してくれる「芦田宿散策マップ」〕
少しひびが入っていますが、”うだつ”のたて壁も漆喰のままですし、オーバーハングした二階の造りも、昔のままのようです。 この家以外にも、旧家があちこちに見られましたので、芦田宿の方々が伝統を重んじていることが感じられました。 芦田宿の出口には、「石打場公園」が整備されていて、「笠取峠の松並木」につながる休憩所となっています。 〔写真:現在も旧家のまま営業を続ける「金丸土屋旅館」〕
前回は新緑の頃でしたが、今回は晩秋の時期で、松並木に加えて、紅葉や落葉がキレイでした。 この写真では、松並木が隅の方に映り、少し可哀想なのですが、大切に手入れされているようで安心しました。 写真の撮影場所は、国道142号と交差する場所ですから、また車でも来たいなと思い、先に進みました。 〔写真:晩秋の時期で、紅葉や落葉がキレイだった「笠取峠の松並木」〕
笠取峠の石碑や標識は、何箇所かにありますが、左の写真の石碑は、長和町側に入ってから、2本の道標が建つ付近にありました。 この後は、国道142号から離れて、「中山道原道」の標識に従って歩き、最後は松尾神社の境内を抜けて、長久保宿に到着しました。 長久保宿からは、JRバス関東が、丸子町経由JR上田駅前までのバスを運行していますので、今回は予定時間通りのバスに乗車して、無事に上田駅前のホテルに入ることが出来ました。(25,000歩) 〔写真:何箇所かにある笠取峠の石碑(長和町側)〕 |
||||||||||||||
| |
| 長久保 〜 下諏訪 (10日目:約10時間、推定距離 約30km) | ||||||||||
2013年11月20日 |
||||||||||
中山道最大の難関である和田峠に向うため、JRバス関東の長久保営業所を後にして、早速長久保宿の横町から中山道に入りました。 昨日通った竪町にも本陣跡や「釜鳴屋」などの旧家が目を引きましたが、横町には旅籠「辰野屋」が、ほぼ昔の姿を留めていました。 長久保宿から出て国道142号に入り、コンビニで昼食のおにぎりを買い込むと、ペースを上げて、しばらく国道を進みました。 〔写真:ほぼ原形を留める、横町の旅籠「辰野屋」〕
この道標に従い、落合橋から旧道に入り、一旦国道に戻りますが、青原の「水明の里公園」から和田宿までは、旧道を進みます。 晴れているのですが、風が強く、黒い雲が時々流れてくる天候で、帽子を押さえながら歩くことになりました。 途中には、左の写真のように、茅葺のバス停もあり、道案内の青い道標も目を引きます。 〔写真:茅葺のバス停と道案内の青い道標〕
「和田宿ステーション」は、少し中山道から離れており、上り道と強い風に悩まされて遅れてきましたので、残念ながらパスです。 和田宿には、歴史的に貴重な建造物や、古代の黒曜石に関する資料館など、興味を惹かれますが、時間が足りません。 冠木門のある「和田宿本陣」などの写真を撮って、先に進みます。 〔写真:冠木門のある「和田宿本陣」〕
「本亭旅館」については、前回は旅館前に駐車する車も見かけたのですが、2012年から営業を休止されているようです。 高札場跡から先に進み、一里塚碑のある国道の鍛冶足交差点を渡り、しばらく旧道を進み、和田発電所付近からは国道を進みました。 唐沢橋を過ぎると、古道の「唐沢一里塚跡」の道案内があり、国道を離れました。 〔写真:2012年から営業を休止されている「本亭旅館」〕
「歴史の道」の案内板もあり、中山道の一部変更で取り残された江戸から51番目の一里塚とのことです。 再び国道に戻り、先を急ぎます。 ようやくその先に、気温3℃の電光掲示板と男女倉口のバス停が、国道142号の分かれ道に見えてきました。 〔写真:中山道の一部変更で取り残された江戸から51番目の一里塚「唐沢一里塚跡」〕
「東餅屋」3.5km、「永代人馬施行所(通称:接待)」1.5km、「三十三体観音像」0.2kmの距離案内が出ていました。 午後1時30分と、予定よりも少し遅くなりましたが、時々太陽が顔を出すなど、天候は持ちこたえています。 足元には、落ち葉が敷き詰められていて、柔らかい感触が上り道のつらさを軽減してくれます。 〔写真:「歴史の道」の案内板(頂上まで4727m)がある中山道の登り口〕
石造物調査のパート仕事を思い出しましたが、写真を撮り、軽く一礼して先に進みます。 時々顔を出す太陽から、明るさと暖かさをもらえて、上り道を順調に進むことが出来ました。 20分ほどで、車の音が近くなり、国道と合流する広場がある「接待」に到着です。 〔写真:休憩小屋と「三十三体観音像」〕
和田発電所付近でも見かけた「ゴミ無し童地蔵」が、広場の隅で手を合わせていましたが、来訪者に願いが伝わると良いですね。 ちょうど午後2時ですから、昼食のおにぎりを食べて、早々に出発です。 手元の高度計で1290mですから、和田峠の頂上まで、まだ300m程度の登りが残っている状況です。 〔写真:「永代人馬施行所(通称:接待)」〕
「殉職警官の碑」を過ぎ、「避難小屋」がある付近の沢沿いの道では、積雪が多くて、雪道を歩くことになりました。 少し心細くなったところで、思いがけず対面からストックを持ち、勢いよく歩いてくるご夫婦がみえて、元気が出ました。 「広原一里塚」を過ぎたキャンプ場付近で、やはり対面からの男性1人に、下諏訪側の様子を尋ねたところ、「ほとんど雪はありませんよ」とのことで、予定通り進むことに決めました。 〔写真:落ち葉の上に、積雪が多く残る「広原一里塚」〕
日暮れまでに下諏訪側の山道を終えないと危険ですから、休憩も取らずに急な道を、「西餅屋跡」付近まで降りて、一服して残りのおにぎりを食べました。 この後は、下諏訪まで下りの国道142号の歩道を、頭部にLEDライトを装着し、手持ちの懐中電灯を併用して、暗闇の中を進みました。 途中にある「水戸浪士墓」や「木落し坂」は、前回写真も撮っているのでパスして、とにかく先を急ぎました。 〔写真:少し積雪がある「古峠(和田峠)」とお世話になった「歴史の道」の案内板〕 いよいよ下諏訪の街灯りが近くなってきた頃に、足を痛めてしまい、帰路の列車時間にもギリギリとなり、下諏訪の「三角八丁」をショートカットして、やっと深夜に帰宅することが出来ました。(45,000歩) |
||||||||||
| |
| 下諏訪 〜 洗馬 (11日目:約7.5時間、推定距離 約20km) | |||||||||
2013年11月27日 |
|||||||||
下諏訪駅に掲示されている「三角八丁」エリア(左の写真)をショートカットして帰宅しましたので、今回は北側から下諏訪宿に入る道で、三角形の頂点からスタートです。 したがって、下諏訪駅から「三角八丁」エリアの中央を北上して、「諏訪大社下社春宮」付近から中山道に入り、下諏訪宿を時計回りにグルリと通り抜けて、春宮大門交差点から西へ向うコースとなります。 さらに、今井の番所跡や本陣がある岡谷市内を通り、塩尻峠から塩尻宿を経て洗馬宿を目指すことにしました。 〔写真:下諏訪駅の「三角八丁」エリアと御柱祭り紹介掲示〕
初めて参詣した「諏訪大社下社春宮」の「幣拝殿」は、秋宮と同様の構造とのことですが、立地の違いでしょうか、近くで拝観させて頂いたためか、見事な建築物と感じました。 これまで「諏訪大社下社秋宮」は、何度か参詣していますが、同じように広大な敷地と建物を持つ春宮があることに、改めて驚くばかりです。 この地方の方々の信仰の深さと、思い入れというか、御柱祭りも凄いと思うのですが、それ以上のものがあるのだと認識し直しました。 〔写真:初めて参詣した「諏訪大社下社春宮」の「幣拝殿」〕
JR下諏訪駅の観光案内所でも勧めていただいたことがあり、この機会に是非拝観しておきたいと考えました。 赤い橋を渡り、地元の観光協会の方がお土産を並べている前を通り、掲示板のお参りの仕方の説明に従い「万治の石仏」を拝観しました。 本当に独特なフォルムの石仏で、岡本太郎画伯が喜びそうな、貴重な文化財だと感じました。 〔写真:岡本太郎画伯が絶賛した「万治の石仏」〕
歩き進むと、53里目の一里塚跡や「伏見屋邸」があり、宿場町の雰囲気を感じる中に、立派な門構えの「本陣遺構」が見られます。 いつもの通り、門前を素通りしましたが、貴重な文化財として大切に保存されているようです。 その先に、「聴泉閣かめや」の看板が見えてきました。 〔写真:立派な門構えの「本陣遺構」〕
同様に、問屋場跡の壁画や、くるくる回る石球も、改めて写真に撮りましたが、この場所にも、両街道で併せて4回目の訪問なのです。 そうは言っても、年月の経過に伴い、何らかの変化があり、この石碑の位置変更や、御柱グランドパークの廃止などに、”変化”を感じます。 そうした変化についての興味も尽きませんが、本陣や諏訪大社のように変わらないものも、これまで通り大切に保存していただきたいものです。 〔写真:「甲州道中・中山道合流之地」の石碑と、横に追加された説明板〕
ここの休憩明けに、とんでもない方角違いをしてしまい、30分以上歩いても、なかなか今井の番所跡や本陣に到達しません。 間違えて北方への道を歩いていたためで、たどり着いたのが、国道20号バイパス近くの「出早雄小萩神社」公園でした。 農作業中の地元の方に相談したところ、「中山道は、かなり南に戻らないとダメ」と教えてもらいました。 〔写真:道を間違えてたどり着いた、国道20号バイパス近くの「出早雄小萩神社」公園〕
塩尻峠の上りは急なのですが、道を間違えた時間ロスを取り返そうと頑張りましたので、ほぼ予定時刻に展望台に到着出来て、諏訪湖の眺望を楽しみました。 今回は、富士山の世界文化遺産登録に伴う紹介看板が目に付き、「関東富士見百景」の一つとして、富士山も遠望することが出来ました。 ところがこの後、再び方向違いをして、キャンプ場の方に迷い込み、二度目の時間ロスをしてしまい、昼食抜きの強行軍となりました。 〔写真:富士山の世界文化遺産登録に伴う紹介看板と塩尻峠展望台からの眺め〕
塩尻宿の手前で、この地方らしい建物として「本棟民家」の説明看板がありましたので、宿内の「堀内家住宅」と同様に、写真を撮りました。 塩尻宿には、旧家もいくつか残り、目を引かれる場所なのですが、時間が不足してきましたので、立ち止まって写真を撮り、また先に進むの、忙しい繰り返しになってきました。 いよいよ塩尻宿を出る頃には、雪雲も流れて薄暗くなり、「平出遺跡」から先は、写真も撮り難くなって来ました。 〔写真:この地方らしい建物として説明看板のある「本棟民家」〕
何とか歩くペースも上がり、列車に間に合う見通しを得た辺りで、「中山道と善光寺道のわかされ」が目に入りましたので、暗い中でしたが写真撮影をしました。 映りの悪さはご容赦頂き、明るさと色調の補正を施しましたので、帰路の列車に間に合ってホッとした気持ちを汲んで、ご覧頂ければ幸いです。(29,000歩) 〔写真:暗い中で写真撮影をした「中山道と善光寺道のわかされ」〕 |
|||||||||
| |
| 洗馬 〜 贄川 (12日目:約3時間、推定距離 約10km +再歩分:約3時間、約6km) | ||||||
2013年12月1日 |
||||||
日暮れが早い季節なので、計画時点から考えておけば、先を急いで道に迷ったり、薄暗くて写真が撮れない問題も予防できたと反省です。 この日は、下諏訪宿を再訪して、岡谷市今井付近を歩いた後、JR洗馬駅まで列車で移動して、中山道に戻ってJR贄川駅まで歩きました。 間違えた出早口の交差点から正しい道を進むと、一里塚跡があり、その先には旧家が並び、「今井番所跡」や、見事な松や屋敷林のある「今井本陣」も見えてきました。 〔写真:見事な松や屋敷林のある「今井本陣」〕
この「中山道」の石碑を飛ばしては、これまでの「旧街道一人歩き」の苦労が水の泡になってしまいます。 趣味として気ままに歩いていますが、いい加減にはしたくありませんので、撮影しながらホッとしました。 塩尻峠への登り口まで歩き、ファミレスで昼食を摂り、JR岡谷駅までの移動には、市民バスの「シルキーバス」を利用させてもらいました。 〔写真:岡谷市今井付近にある「中山道」の石碑〕
駅前には、大きな「集落(旧洗馬宿)案内板」が建ち、地元を紹介したいとの地域の人々の気持ちが旅人にも伝わります。 洗馬宿には、中山道と善光寺参りの旅人が行き来して、往時はにぎやかだったようですが、その名残りの建物が今でも残っています。 また、高札場跡の石碑や案内板にも洗馬宿の繁栄が偲ばれます。 〔写真:高札場跡の洗馬宿の繁栄が偲ばれる石碑や案内板〕
本山宿も、入り口に「下町石造群」があり、旧家が軒を連ねて残されているなど、往時には繁栄した宿場だったことが判ります。 ”そば切り”発祥の地との看板もあり、信濃の国の名物として、今も食べられているような、お蕎麦の故郷なのでしょう。 計画を見直したお陰で、旧宿場町をゆったりとした気分で、気持ち良く歩くことが出来ました。 〔写真:旧家が軒を連ねて残されている本山宿〕
いよいよ木曽路の始まりですが、車で通ると、周りの景色に見とれて、左の写真の有名な石碑や桜沢の史跡なども見過ごしてしまいがちです。 桜沢の史跡は、明治天皇の小休所なのですが、先の有名な石碑と併せて、往時の桜沢集落の重要さが伺われます。 また、「初期中山道」は、岡谷から三沢峠を越えて小野宿を通り、牛首峠を経て桜沢に出る小野街道だったとの案内板も建っていました。 〔写真:日出塩から先の川沿いにある「是より木曽路」の石碑〕
見直した計画により、次の区間である奈良井宿や鳥居峠を、余裕を持って歩くためにも、この日はJR贄川駅までにしておきました。 それでも、夕闇が迫る午後4時にJR贄川駅に到着しましたので、左の写真でも判るように薄暗く寒い駅から、明るくて暖かい列車に乗車して、帰路に付きました。(15,000歩+8,000歩) 〔写真:夕闇が迫るJR贄川駅と駅前の店〕 |
||||||
| |
| 贄川 〜 藪原 (13日目:約6.5時間、推定距離 約15km) | ||||||||
2013年12月4日 |
||||||||
JR贄川駅には9時37分に到着して、すぐに復元された「贄川関所・木曽考古館」の前を通り、旧家も残る贄川宿を抜けて、奈良井川に近い旧道を進みました。 鉄道の古いトンネル跡の先には、「押込一里塚跡」があり、国道19号に合流して、すぐに左の旧道に入った後、また国道に戻ります。 しばらく進むと、道の駅「木曽ならかわ」・「木曽くらしの工芸館」があり、少し早いのですが食事処で、「そば定食」の昼食を摂りました。 〔写真:復元された「贄川関所・木曽考古館」〕
旧家が中山道沿いに軒を並べていますが、ほとんど漆器関係の店のようで、現在でも漆器生産と販売が行われています。 伝統的建造物としての街並み保存については、地区としても取り組んでいることが、現地でも、後で見たHPからでも伺うことが出来ます。 宿場町とは違いますが、伝統的な産業継承にもつながる、貴重な街並みではないでしょうか。 〔写真:漆器関係の旧家が中山道沿いに軒を並べる「漆器の町平沢」〕
奈良井川と中央本線の線路を渡ると、「奈良井宿」に近づきます。 JR奈良井駅から先は、一般車両の駐車場が無く、宿場町としての「奈良井宿」は、観光シーズンには歩行者天国のような状態になります。 案内板にあるように「重要伝統的建造物群保存地区」として、官民学の連携と地元住民の協力により、観光客に人気があるスポットになっています。 〔写真:「木曽路 奈良井宿」の標識と地図入りの案内板〕
奈良井宿には観光客が多くて当たり前なのですが、初冬のオフシーズンとはいえ観光客や地元住民が少なくて、写真を撮りながら、時代をさかのぼった様に感じてしまいます。 午後1時前になり、鳥居峠に備えて、中町でトイレ休憩を済ませます。 中町を先に進むと、今なお中山道の面影を色濃く残す「奈良井宿上問屋資料館」付近にさしかかりました。 〔写真:今なお中山道の面影を色濃く残す「奈良井宿上問屋史料館」付近〕
他の宿場町にも残されていますが、奈良井宿では広さもあり、昔の形を残しているようです。 この辺りで、ようやく観光客のグループに出会いましたが、信じられないほどの人気(ひとけ)の無さで、オフシーズンの奈良井宿を満喫できました。 上町の外れには高札場と水場があり、少し上り道となり、若宮神社と鎮神社を過ぎると、右手の石段から、鳥居峠への登り口に入ります。 〔写真:中町と上町の境にある「鍵の手」〕
やはり上り道はつらいものですが、途中に展望台や休憩所もあり、小春日和の天候に恵まれて、ハイキング気分を楽しみました。 一里塚を過ぎて、前回雨宿りをさせてもらった鳥居峠近くの「峰の茶屋」も懐かしく、「御岳神社遥拝所」から先も”熊除けの鐘”を鳴らして順調に進みました。 藪原宿への下り道の途中で、山道の保全管理の方々にお会いしましたが、観光客の一人として道の整備をして頂き、有り難いと思いました。 〔写真:前回雨宿りをさせてもらった鳥居峠近くの「峰の茶屋」〕
前回は雨の中でしたから、周囲を見る余裕も無く、記憶も不確かなのですが、消防署も公衆便所も新しくなったような気がします。 藪原宿へ下りてくると、宿場紹介の案内板の数々と、下校途中の元気な子供達が印象に残りました。 地域の方々が活発に活動されているようですし、有名な「おろく櫛問屋」も店構えが健在で嬉しくなりました。 〔写真:藪原宿で有名な「おろく櫛問屋」〕
旧街道を歩いていて、古いものが滅びてゆく感傷を味わうことが多いのですが、新しいものに置き換わり、古いものの中から価値のあるものだけが残され、地域として再生されてゆくことを望みたいと思います。 ちょうど「中山道六十九次」の中間宿である藪原宿で前半を終えましたので、冬休み明けから「中山道(2回目)〔後半〕」に挑戦といたします。(23,000歩) 〔写真:夕暮れ近くに自動点灯したJR藪原駅〕 |
||||||||
| |